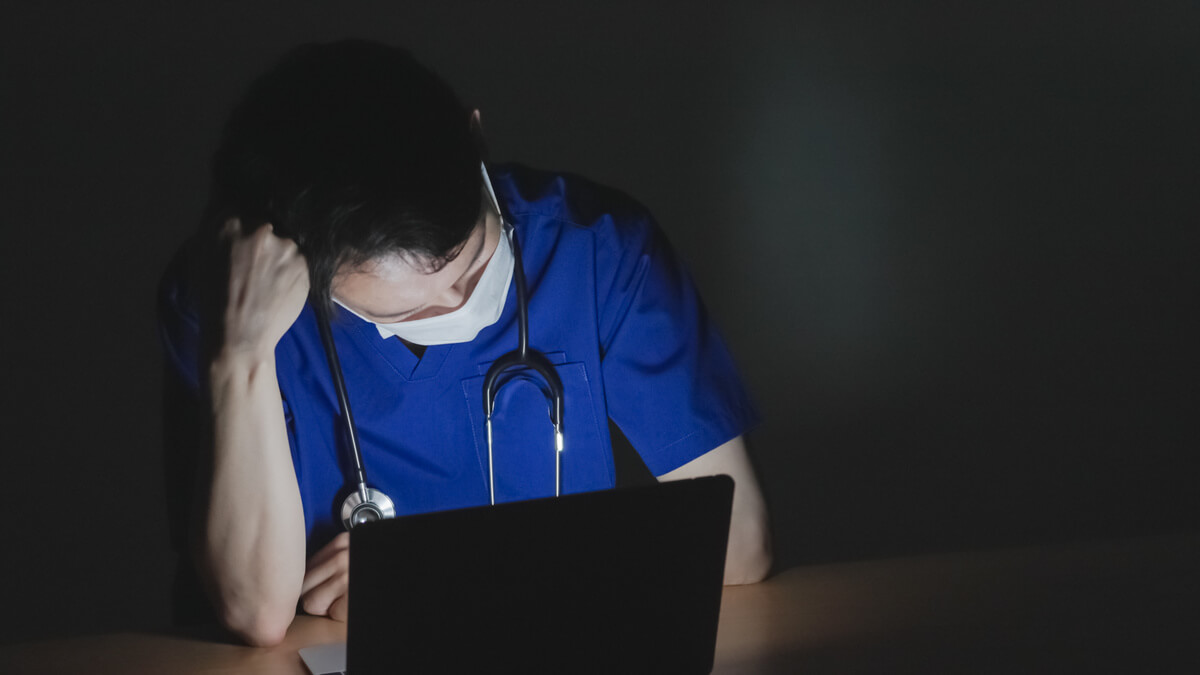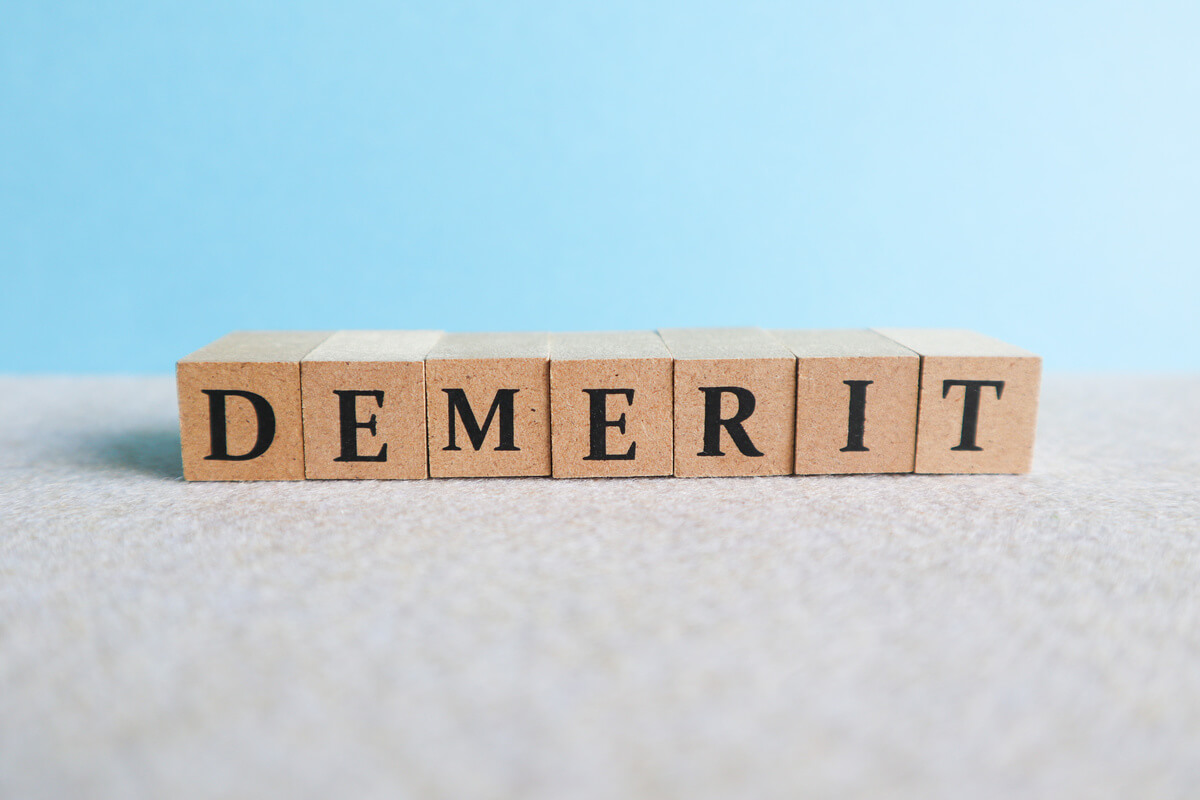キャリアアップやライフスタイルの変化によって、転職を考えている医師もいるのではないでしょうか。どんな理由で転職するかや退職の方法について、悩んでいる医師もいるかもしれません。
この記事では、医師の転職理由でもっとも多いものを紹介します。また、病院を退職する際に、上手な退職理由の伝え方と退職までの流れや、転職で失敗しない方法もお伝えします。
この記事を読めば、あなたの転職に役立つ情報が得られるでしょう。転職をしようと考えている医師は、ぜひ最後までお読みください。
医師が転職する理由

医師が転職する理由は、どのようなものが多いのでしょうか?ここでは、医師の転職理由でもっとも多いものを7つ紹介します。
- ライフスタイルの変化
- 激務だった
- 給与に不満があった
- 人間関係に悩んでいた
- 人事異動
- キャリアアップを考えている
- 将来的に不安がある
ライフスタイルの変化
医師の転職理由のひとつに、ライフスタイルの変化があります。例えば、結婚や出産、子育てなどで、家庭と仕事のバランスを考えるようになった場合です。また、趣味や自己啓発など、自分の時間を大切にしたいと思うようになった場合もあります。
ライフスタイルの変化に伴って、勤務形態や勤務地、勤務時間などに柔軟性が求められます。しかし、現在の病院では、そのような要望に応えられない場合が多いです。そこで、自分のライフスタイルに合った働き方ができる病院や職場を探すために、転職活動を行います。
激務だった
医師の転職理由に、激務だったということがあります。医師は、長時間の勤務や夜勤、当直などで、体力的にも精神的にも疲弊してしまうことも多い職種です。また、医療ミスや訴訟などのリスクも常に背負っています。
激務によって、医師はストレスや疲労を感じるだけでなく、健康や生活の質にも影響を受けます。さらに、激務が原因で、医療に対する情熱ややりがいを失ってしまうことも考えられます。
そこで、自分の体と心の健康を守るために、もっと働きやすい環境を求めて、転職することを決意する医師もいます。
給与に不満があった
給与への不満も転職理由の1つにあげられます。医師は、高い専門性と責任感を持って、人々の健康と命を守る仕事をしています。しかし、その仕事に見合った給与が必ずもらえているとはいえません。
医師の給与は、病院や診療科、勤務年数などによって異なります。また、医師の給与は、税金や保険料などの負担が大きく、手取り額は思ったより少ないことが多いです。
そこで、自分の労働に見合った給与を得るために、もっと高い給与がもらえる病院や職場を探すために、転職をしようと考えます。
人間関係に悩んでいた
医師の転職理由のなかでも、多いもののひとつに、人間関係に悩んでいたということがあります。
人間関係に悩む原因は、さまざまです。例えば、コミュニケーションの不足における情報の不足、パワハラやセクハラ、派閥やいじめなどです。また、人間関係に悩むことは、医師の仕事の質や効率にも影響を与えます。
そこで、自分の仕事に集中できるように、もっと良好な人間関係が築ける病院や職場を探すために、転職をするのです。
人事異動
病院の人事異動で、望まない分野や地域への配属が決まることもあります。こうした人事判断に不満を持ち、転職を選択する医師もいるのです。
キャリアアップを考えている
臨床医としてのキャリアに限界を感じ、管理職を目指したり、研究職に就きたいと考える医師もいます。
その場合、所属病院内での配置転換が難しければ、転職して新たなキャリアを築こうとするのです。
将来的に不安がある
定年がないといわれている医師ですが、体力の衰えによって医師として働き続けることに限界を感じることもあります。
このように将来に不安を感じ、自分のキャリアを続けられそうな場所を探して転職をする医師もいます。
医師が転職する際の退職理由の上手な伝え方

医師が転職する際に、退職理由を上手に伝えることはとても重要です。ここでは、退職理由の上手な伝え方と、例を紹介します。
前向きな姿勢で伝える
退職する病院には、できる限り前向きな姿勢で退職理由を伝えることが大切です。
退職後も好意的な関係を保つため、否定的な表現は避け、新たなキャリア形成を目指す気持ちを伝えましょう。
退職理由の上手な伝え方の例
退職理由は以下のような言葉で伝えるとよいでしょう。
- キャリアアップを目指す場合の転職なら、「新しい環境で力を発揮したい」
- 人間関係を改善するための転職なら、「周りと意思疎通を取りながら働きたい」
- ライフスタイルの変化なら「家庭の事情で勤務時間の見直しが必要」
不平不満が退職の理由だとしても、ポジティブな言葉で退職理由を伝えることが退職後も関係を良好に保つために必要です。
医師が退職するまでの流れ

退職の流れを押さえておくと、転職活動も逆算して活動しやすくなります。一般的には、退職を決めてから、退職するまでは以下の流れで進んでいきます。
- 退職の意思を病院に伝える
- 退職願を提出し、退職日を決定する
- 後任者の引き継ぎや必要な事務手続きを行う
- 退職当日、上司・職場のメンバーに退職の挨拶をする
退職までには2~3ヶ月程度の期間が必要です。転職活動も退職までの時期を考えて逆算して行いましょう。
また、業務引き継ぎなどに十分な時間をとることも重要です。円滑な退職に向けて事前の準備と周囲への配慮は欠かさないようにしましょう。
医師の転職で失敗しないためのポイント
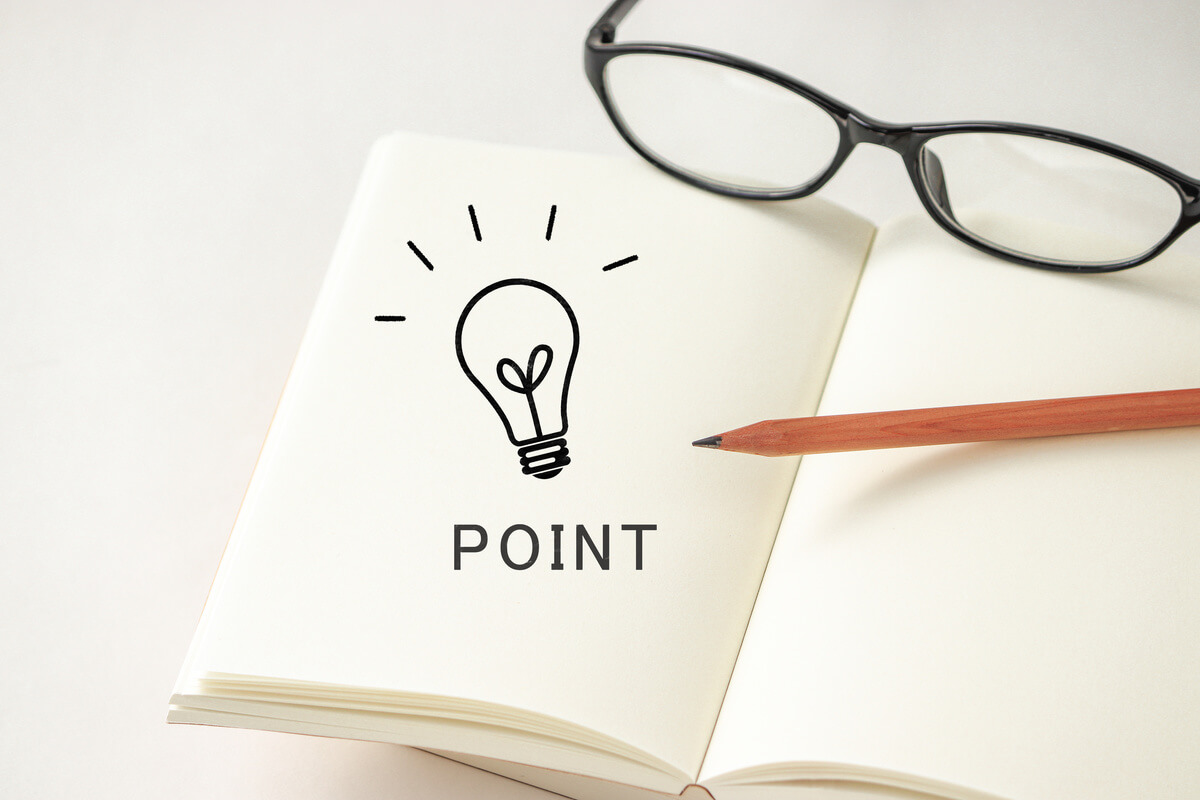
医師の転職で失敗しないためには、以下の3つのポイントを押さえておくことが大切です。
- 転職に求める優先順位を決める
- 焦って転職先を決めようとしない
- エージェントを活用する
それぞれを詳しく解説します。
転職に求める優先順位を決める
転職に求める優先順位とは、自分が転職先に望む条件や目標を明確にすることです。
例えば、給与や勤務時間、勤務地、診療科目、研修制度、人間関係などが挙げられます。これらの条件は、医師にとって重要な要素ですが、すべてを満たす転職先はなかなか見つかりません。そこで、自分にとって最も優先度の高い条件を決めておくことが、医師の転職で失敗しないためのポイントになります。
優先順位を決める方法としては、以下のようなステップがあります。
- 自分が転職を考える理由を整理する
- 転職先に望む条件をリストアップする
- 条件ごとに優先度をつける
- 優先度の高い条件を3つ程度に絞る
このようにして、自分の転職に求める優先順位を決めることで、転職先の選択肢を絞り込むことができます。また、自分の転職の目的や方向性を明確にすることで、転職活動におけるモチベーションや自信も高まるでしょう。
焦って転職先を決めようとしない
医師の転職で失敗しないためのもう一つのポイントは、焦って転職先を決めようとしないことです。医師の転職は、一般的な転職とは異なり、病院の採用サイクルや医師の人材市場の動向に影響されます。
そのため、転職先がすぐに見つからない場合や、自分の希望に合う転職先が少ない場合があります。このような状況になると、焦ってしまって、自分の優先順位とは異なる転職先に飛びついてしまうことがあります。しかし、これは失敗する原因になります。
焦って転職先を決めようとしないためには、以下のようなことを心がけるとよいでしょう。
- 転職活動に十分な時間をかける
- 転職先の情報を多角的に収集する
- 転職先の現場を見学する
- 転職先の医師やスタッフと話す
- 転職先の評判や口コミを調べる
これらのことを行うことで、転職先の実態や自分との相性をより深く知ることができます。また、自分の転職に求める優先順位と転職先の条件を比較することで、自分にとって最適な転職先を見極めることができるでしょう。
転職エージェントを活用する
医師の転職で失敗しないための最後のポイントは、転科エージェントを活用することです。エージェントとは、医師の転職をサポートする専門のコンサルタントのことで、以下のようなメリットがあります。
- 転職市場の最新情報や転職先の内部情報を提供してくれる
- 自分の転職に求める優先順位やキャリアプランを一緒に考えてくれる
- 転職先の紹介や面接の調整をしてくれる
- 転職先との条件交渉や退職手続きのサポートをしてくれる
エージェントを活用することで、医師の転職活動を効率的かつ効果的に進めることができるでしょう。また、エージェントは医師の転職に関する専門知識や経験を持っているので、転職に関する悩みや不安にも寄り添ってくれます。
まとめ
医師の転職理由で多いものを紹介し、上手な退職理由の伝え方と退職までの流れも解説しました。
転職で失敗しないためには、自分の中で優先順位をつけることが大切です。また、退職までの期間を逆算して、転職活動を行うとスムーズに転職できるでしょう。
転職を考えているなら、転職エージェントを利用してみてはいかがでしょうか。どの転職エージェントを使ったらよいか、迷っているなら「メディカルジョブ」がおすすめです。
メディカルジョブでは、キャリアアドバイザーがヒアリングを行い、最適な転職先を選んでくれます。また、転職先だけではなく、アルバイト先も豊富に用意しているので、自分にぴったりの転職先が見つかるでしょう。
これから転職活動をはじめようと考えているなら、ぜひメディカルジョブに登録してみてはいかがでしょうか。